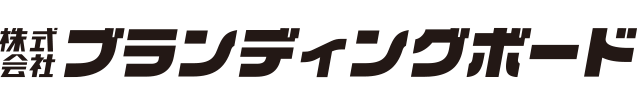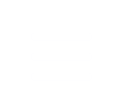コラム
Column

Canvaが仕掛けた斬新な野立て看板キャンペーン
2025年7月4日

街を歩いていて、ふと目にした広告に「やられた!」と膝を打った経験は、あなたにはあるだろうか。思わず二度見し、スマホを取り出して写真を撮り、誰かに「これ、すごくない?」と送りたくなるような、そんな出会いだ。
多くの場合、そうした広告は息をのむほど美しかったり、胸を打つキャッチコピーが書かれていたりするものだ。しかし、もしその広告が、どう見ても「失敗作」だったら?
舞台はロンドン、ウォータールー駅近くの古びたレンガの壁。そこに現れたのは、お世辞にも「完璧」とは言えない、どこか奇妙な看板だった。
巨大すぎるロゴがフレームからはみ出し、「背景を切り抜いた」ら後ろの壁が丸見えになり、あろうことか縦横のサイズまで間違っている。まるで、デザインの授業で「これ、ダメな例ね」と先生が指し示す、残念な見本のような広告群。
だが、これこそがデザインツール「Canva」が仕掛けた、とんでもなくクレバーで、ユーモアに満ちた広告キャンペーンだったのである。これは、広告が自ら「しくじり先生」を名乗り出た、斬新な広告デザインにまつわる記録だ。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/make-the-logo-bigger-a68f2283-5d89-47a1-b398-d31ec579c6cf
広告が「広告」であることをやめた日

まず、この奇妙な看板たちが、何を「しくじっていた」のかを詳しく見ていこう。
一つは、巨大な「Canva」のロゴが、看板の枠に収まりきらずにはみ出してしまっているデザイン。
添えられた言葉は「“When ‘make the logo bigger’ goes a bit too far.”(「ロゴをもう少し大きくして」が、ちょっとやりすぎちゃった時。)」。
ああ、耳が痛い。クライアントや上司との間で、幾度となく繰り返されてきたであろう、あの攻防が目に浮かぶようだ。そして、その横にはCanvaの機能「Brand Kit」の文字が。ブランドの統一感を保つための機能ですよ、と言いたげにさりげなくいる。
別の一つは、看板の絵柄の背景がごっそりと切り抜かれ、看板が設置された壁面の武骨なレンガの背景がむき出しになっている。
まるで、背景透過処理に失敗した画像みたいだ。しかし、これも計算づく。キャプションには「Background Remover(背景リムーバー)」とある。機能を説明するのではない。機能そのものを、看板という物理的な媒体で「やってのけた」のである。その潔さときたら、思わず笑ってしまう。
極めつけは、本来なら横長(16:9)であるべき広告が、なぜか縦長(9:16)で表示されてしまっている看板だ。
「Turns out the 16×9 was actually supposed to be 9×16(結局のところ、16:9は本当は9:16だったらしい)」という、担当者の悲痛な叫びが聞こえてきそうな一文。もちろん、これもCanvaの「Magic Resize」機能を使えば一発で解決できる、というオチがついている。
これらの広告の凄みは、「Show, don’t tell(言うな、見せろ)」という創作の黄金律を、これ以上ない形で体現した点にある。Canvaの機能がいかに便利かを言葉で100回説明されるよりも、この「しくじり」と「解決策」のビジュアルを一目見るほうが、その価値は遥かに雄弁に伝わってくる。
Canvaは、広告を「広告らしいデザイン」にすることを放棄した。代わりに、製品のデモンストレーションそのものに「擬態」することを選んだのだ。
これは、演劇で役者が突然観客に話しかけ、舞台と客席の間の「第四の壁」を壊してしまうようなものだ。広告と現実の境界線を曖昧にし、見る者を傍観者である通行人から、デザインの「あるある」ネタを共有する当事者へと引きずり込む。この巧みな共感のフックこそ、このキャンペーンの核心なのである。
なぜCanvaはこの「自虐ネタ」を仕掛けたのか?

一見すると、これらの広告は自社のユーザーがやりがちな「失敗」を笑いものにする、大胆不敵な自虐ネタのようにも映る。しかし、その裏にはCanvaという企業のしたたかな戦略と、自社製品への揺るぎない自信、そしてユーザーへの深い愛情が隠されている。
そもそも、Canvaというツールは誰のためにあるのか?
それは、アドビのIllustratorやPhotoshopを自在に操るプロのデザイナーというよりは、むしろ「デザインは専門じゃないけれど、仕事で資料やSNS投稿を作らなければならない」という、いわば「非デザイナー」たちだ。彼らにとって、「ロゴをもう少し大きく」「画像の背景を消して」「急にサイズを変えて」といったリクエストは、悪夢のような専門用語が飛び交うパンドラの箱ではなく、日常的に直面する「リアルな悩み」そのものである。
このキャンペーンは、そのリアルな悩みのど真ん中に、これ以上ないほど寄り添ってみせた。「大丈夫、あなたのその気持ち、Canvaはよーく分かってるよ。だって、私たちのツールは、まさにその“しくじり”をなくすために生まれたんだから」と。
広告デザインの固定観念に投げかけたもの

デジタル広告が全盛のこの時代に、Canvaはあえて「野立て看板」という極めてクラシックなメディアを選んだ。しかし、その使い方はまったくクラシックではなかった。彼らは、この物理的な看板がSNSでシェアされ、オンラインで拡散していくこと(バイラル)を明確に計算に入れていた。
「背景リムーバー」の看板広告で、後ろのレンガの壁をあえて見せたように、このキャンペーンは旧来の広告界の常識という分厚い壁に、とんでもない「レンガの一石」を投じたのである。
それは、「フィジカル(物理的)な広告は、デジタルでいかに語られるかをデザインすべきだ」という、新しい時代の広告哲学の提示だった。ロンドンの街角という限定された場所で始まったこれらの看板広告デザインは、瞬く間にインターネットの海を駆け巡り、世界中の人々のタイムラインにその爪痕を残した。
結果として、Canvaは製品の知名度を上げただけではない。「Canva=クリエイティブで、ユーモアがあって、私たちの味方」という、強力なブランドイメージを人々の心に深く刻み込むことに成功したのだ。
結局のところ、Canvaのキャンペーンが私たちの心をこれほどまでに掴んだのはなぜか。それは、この広告が製品の「機能」ではなく、ユーザーの「物語」を語ったからに他ならない。
誰もが一度は経験したことのある、ほんのささいな失敗の物語。冷や汗をかき、頭を抱えた、あの日の物語。そのほろ苦い記憶を、Canvaは「それでいいんだよ」と優しく肯定し、笑い話へと昇華させてくれた。
私たちの周りにある「当たり前」や「常識」、そして「失敗」を、ほんの少しだけ違う角度から眺めてみる。そこにはきっと、人の心を動かすクリエイティブの種が、まだたくさん眠っているに違いない。