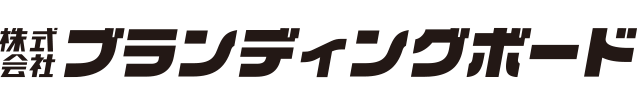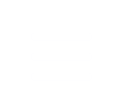コラム
Column

野立て看板とeバイクの冒険:フィンランドに現れた”ありえない風景”
2025年5月1日

「丘はたくさんあるけれど、Haibikeには物足りない。」
このコピーが、妙に頭に残って離れない。よく晴れた春の朝に、フィンランドのとある街角で人々が見たのは、視覚の常識を裏切る風景だった。
その場所にあったのは、野立て看板だった。それは、風景と溶け合い、しかし風景を非日常に変容させる“錯視の仕掛け”の看板であった。
第一の看板には、キリマンジャロがそびえていた。
眼前にはオリンピック・スタジアム、そしてその背後に、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ。しかも、その山の前景には、eバイクにまたがるライダーが立っている。現地の丘に登った人々が錯覚するのだ――「えっ、この街からキリマンジャロが見えるのか?」と。
ふたつ目はマッターホルン。
金色に実った麦畑を前に、これまた一人のライダーが静かに佇んでいる。背景には赤い納屋、そして――あの尖塔のようなマッターホルンが聳えている。ヨーロッパの屋根が、なぜかフィンランドの大地に出現しているのだ。
そして三つ目は、富士山。
湖畔に立ち並ぶ遊園地のカラフルな構造物と、フィンランド・タンペレのランドマーク「ネシンネウラ塔(Näsinneula)」、その向こうに、堂々とした富士の姿がある。しかもこの風景、空と水面が完全な鏡像を成していて、どこか幻想的ですらある。
すべてのビジュアルには共通点がある。
「Haibikeに乗るライダーが、はるかなる山を見つめている」という一点だ。
しかも、この視線は実際の風景に向けられている。看板の前に立てば、山が視線の延長に重なる。まるで現実と幻想が滑らかに溶け合うような、極めて緻密な錯覚演出だ。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/for-the-higher-hills
「見る人を動かす」野立て広告の新境地

このプロモーションは、2025年4月にフィンランド全土で展開された『For the Higher Hills(より高き丘のために)』というHaibikeのキャンペーンだ。
一見すると単なるフォトモンタージュのように思えるかもしれないが、実際の広告効果は、見た者のSNS投稿によって爆発的に拡散した。看板そのものが“登山”の出発点になり、道行く人がライダーの背中を真似して、記念撮影を始める。InstagramやTikTokには、#HaibikeHills というハッシュタグのもと、次々と「私も登った(ような気がする)」投稿があふれた。
つまりこの看板は、視覚を刺激するだけでなく、“行動”を促すトリガーだったのである。
広告のゴールが「商品認知」から「体験共有」へと移行している現在、Haibikeのこの試みは、野立て広告がいかに現代的で、インタラクティブなメディアになりうるかを証明している。
なぜ“山”なのか?eバイクの性能を「登坂力」で語る

ではなぜ、Haibikeはこのようなアプローチを取ったのか?
その理由は、ブランドの中核にある“eパフォーマンス”という理念にある。Haibikeは1995年にドイツで誕生したeバイクメーカーで、とりわけマウンテンバイク領域での電動アシスト技術に定評がある。舗装されていないトレイル、急峻な丘陵、あらゆる傾斜地をものともしない――その性能を語るには、「登る」という動詞が何よりも適している。
けれど、スペックを数字で語ってしまえば、ただの機械の説明で終わる。
Haibikeがとったのは、「登りたい衝動」を、景色の力で掻き立てるという戦略だった。
山は登るためにある。
そして、そこに道がなければ、自分で切り拓けばいい。
このコンセプトが、フィンランドの「少し物足りない丘」に、キリマンジャロやマッターホルンや富士山という“ありえないほど高い丘”を重ねることで、見事に可視化されたのだ。
看板が口コミを生む時代へ

このプロモーションのもう一つの優秀さは、「人が話したくなるネタ」になっていたことだ。
街中のいつもの丘に、なぜか現れるアフリカ、スイス、日本の山々。
違和感こそが最大の吸引力となり、やがて話題が人を伝って移動し、見る人の中で再解釈されてゆく。
こうして看板は、ただの情報発信装置ではなく、「会話の起点」となり、地域を超えてデジタル上で“旅する”存在へと変わっていく。
そもそも野立て看板とは、ある種のランドマークであり、町の風景の一部として人の記憶に残りやすい媒体だ。そこに“風景の上書き”を施すことで、より鮮烈に、より共有しやすくなった。口コミの原動力は、ただのお得情報やスペックの羅列ではなく、「誰かに見せたくなる違和感」である。
Haibikeが見せた、広告の“登り方”

今回のHaibikeのキャンペーンを見て改めて感じたのは、広告の本質は「感じさせること」にある、ということだった。
写真の中のライダーは、実際に走ってはいない。ただ立っているだけだ。
けれど、その静かな佇まいの中に、「登る気満々」なエネルギーがある。
見る者は、自分もあの背中になったつもりで、坂道を登りたくなる。
それはもはや、バイクの性能の説明ではなく、「世界をもう少し高い場所から見てみたい」という欲望のスイッチである。
この「欲望のスイッチ」を押すことが、現代広告の最大の目的だとすれば――Haibikeはまさに、坂の頂で旗を立てることに成功したのである。
広告は時に、商品よりも先に、私たちの視野を広げてしまう。
看板が告げるのは、商品の名前ではなく、「ここから先、もっと上に行けるよ」という、静かな挑発だ。
そう、挑発なのだ。
山を見て、登りたくなるように。
その看板を見て、走り出したくなるように。