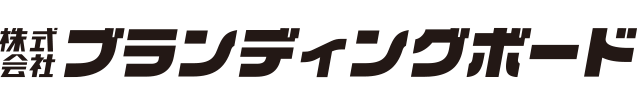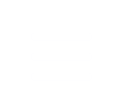コラム
Column

新潟なんて、米と水だけだと思ってた私が浅はかだった件。
2025年8月20日

世の中には『地方創生』だの『地域の魅力発掘』だの、耳障りの良い言葉が溢れかえっている。正直なところ、私にはあの手の話はどうも胡散臭く聞こえるのだ。本当に魅力があるなら、わざわざ『発掘』なんて大層なことをしなくても、自然と人が集まるものだろう、と斜に構えてしまうのである。
かくいう私も、最初は新潟なんて米くらいしか知らない人間の一人だった。親戚の結婚式で、わざわざ東京から車を飛ばして向かった時のことだ。東北自動車道をひた走り、新潟県に入ったあたりからだろうか、景色がガラッと変わった。
それまで殺風景だった灰色の景色が、突然、見渡す限りの緑に変わったのだ。それはもう、圧倒的な稲穂の海。風が吹くたびに、ざわざわと波打つ様は、まるで生き物を見ているようだった。高速を降りて、一般道をしばらく走らせる。田んぼ、田んぼ、そしてまた田んぼ。どこまで行っても田んぼなのである。そんな景色を見ているうちに、私の腹は妙な音を立て始めた。
「……米、食いてぇ」
無性にご飯が食べたくなったのだ。頭の中は、真っ白なご飯でいっぱいだった。そんな折、まるで神の啓示かのように、ぽつんと現れたのが、昔ながらの食堂だった。

店構えは至って地味。だが、その地味さが、逆に私を惹きつけたのかもしれない。ふらりと暖簾をくぐり、カウンター席に腰を下ろす。メニューを眺めるまでもなく、私の口から出たのは「餃子ライスとラーメンください」という、もはや条件反射的な言葉だった。
まず、コップに注がれた水を一口飲んだ。――なんだ、これ? 思わず、隣の席に座っていた見知らぬおじいちゃんに話しかけそうになった。『この水、どこで売ってるんですか?』とでも聞こうとしたのだろうか、私。たかが水、されど水。こんなに瑞々しい水を飲んだのは、いつ以来だろう。いや、もしかしたら人生で初めてかもしれない。大げさだと思われても構わない。それが私の偽らざる感想だったのである。
――で、次に餃子ライスとラーメンが運ばれてきたのだが、まあ、ラーメンは普通に美味かった。餃子も悪くない。問題は、いや、問題じゃない、驚愕したのは、真っ白に盛られたご飯だったのだ。一口。――もう一度言う。一口食べただけで、私は悟った。これは、米と水だけで成立する、完璧なご馳走なのだと。
新潟は米どころだとは、もちろん知っていた。だが、その時、私は確信したのである。「ここは米どころであると同時に、水どころでもある」と。雪解け水が山から流れ出し、やがて地下水脈となり、田畑を潤し、人々の喉を潤す。あの水なくして、あの米はありえない。そう、新潟の食の魅力は、まさにその「水」に凝縮されている、と言っても過言ではないだろう。日本海の海の幸も、豊富な山菜も、そして言わずもがなの日本酒も、全てはこの清らかな水あってこそなのである。

さて、『衣食住』の『食』については、もはや語るまでもないだろう。次は『衣』である。
まさか、雪国のイメージが強い新潟で、日本のニット生産のトップクラスを誇る街があるなんて、誰が想像できただろうか? 五泉市とか見附市とかいうらしいのだが、正直なところ、私はそこまでファッションに頓着しない人間なので、ふーん、そうなのか、としか思わなかった。が、しかし、考えてみれば当たり前なのだ。あの厳しい冬を乗り越えるには、それなりの温かさ、そして機能性、さらには少しでも気分を上げるデザイン性が求められる。結果的に、彼らは最高のニットを作り上げた。なるほど、理に適っているではないか。人は必要に迫られると、とんでもないものを生み出すというのは、まさにこのことだろう。もしかしたら、新潟の人は密かにオシャレなのかもしれない。普段は作業着だが、ここぞという時には、とびきりのニットを身につけて、しれっと決めている――なんて想像すると、ちょっと面白い。

そして、『住』である。新潟の冬は寒い。いや、最近は夏も東京以上に暑い時があるから、もはや『気候が厳しい』と表現する方が正確だろう。そんな環境で、快適な生活を送るなど、並大抵のことではないはずだ。しかし、彼らはそれを実現している。先人の知恵と、現代の建築工法の融合。分厚い壁、二重窓、そして床暖房。一歩家の中に入れば、そこはまるで別世界なのである。外の吹雪や猛暑が嘘のように、穏やかで快適な空間がそこにある。これはもう、住まいの芸術、と呼ぶべきではないだろうか。快適性への飽くなき追求が、結果としてハイスペックな住環境を作り出した、というわけだ。

最後に『人』である。これはもう、住んでみないと分からない、としか言いようがない。テレビやネットで流れてくるような、『人情味溢れる』だの『温かいおもてなし』だのといった紋切り型の表現では、到底伝えきれない複雑な何かがあるのだ。厳しい自然の中で培われた芯の強さ、それが時折、不器用な優しさとして現れる。まるで、分厚い雪の下に隠された清流のように、静かに、しかし確かに流れている優しさ。私はまだ、その清流のすべてを見たわけではないが、何度か触れる機会があった。そしてその度に、『ああ、これは本物だ』と、妙に納得させられてしまうのである。

新潟の魅力。それは、決して派手ではない。むしろ、地味で、堅実で、しかし一度触れると、その本質的な豊かさに深く魅了される。衣食住、そして人。すべてが厳しい環境の中で磨き上げられ、本物としてそこに存在している。あの時の水と米の一口は、まさにその『本物』への入り口だったのである。あの時以来、私は新潟を少しだけ尊敬の目で見るようになったのだ。まったく、やれやれである。