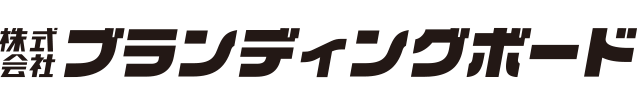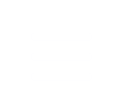コラム
Column

野立て看板に心奪われる理由(もしくは、看板の面白さを「発見」するインドの芳香剤のたくみな看板デザインについて)
2025年7月14日
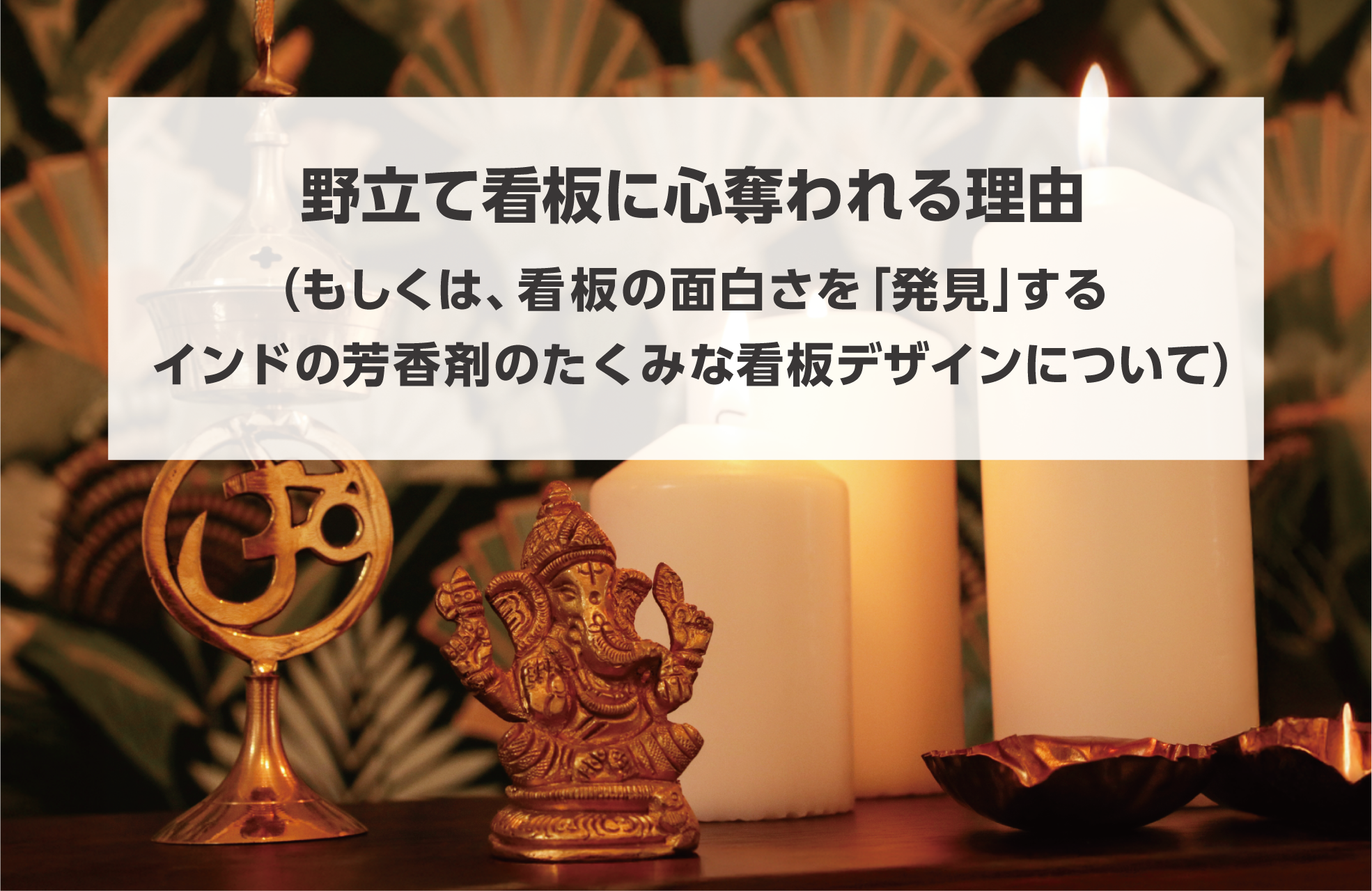
クルマの窓から流れていく、見慣れた国道沿いの風景。
そこに林立する、おびただしい数の野立て看板。
正直に言おう。かつて僕は、それらのほとんどを、風景を汚すノイズだと思っていた。思考の隙間に無理やりねじ込まれる、招かれざる情報。デジタル広告が僕らの興味をアルゴリズムで正確に狙い撃ちしてくる時代に、こんなアナログで、不特定多数に漠然と呼びかける手法が、まだ生き残っていること自体が不思議だった。
果たして、広告は風景の邪魔者でしかないのだろうか?
僕らの意識を素通りしていくだけの、空虚なメッセージの残骸なのだろうか?
そんな、傲慢で知ったかぶりな決めつけをする僕の脳天を、ハンマーで揺らすような衝撃を与えた看板広告を見つけた。
これは、「発見」だ。見事なクリエイティブだった。
21日間の物語を売る、インドの芳香剤

その広告は、インドの芳香剤ブランド「Iki」のキャンペーンだった。「21 Days of Freshness」という、なんとも直球なタイトルのシリーズ。僕が最初に目にしたのは、一台の高速鉄道が疾走する、鮮やかな黄色の看板だった。
「THE WORLD’S LONGEST TRAIN JOURNEY TAKES 21 DAYS.(世界最長の鉄道旅行は21日かかる)」
え?、鉄道の広告じゃない。隅っこに、小さな芳香剤のパッケージがちょこんと置かれている。そして、その横にはこう添えられていた。「About the number of days Iki keeps you fresh!(Ikiがあなたをフレッシュに保つ日数について)」
うまい! 知的で、ウィットに富んだコミュニケーション!
このキャンペーンの骨子は、驚くほどシンプルだ。Ikiのミニゲル芳香剤の香りが「21日間」持続するという製品特徴。それを伝えるために、彼らが選んだ手法は、直接的に「21日間も長持ちします!」と叫ぶことではなかった。そうではなく、世の中にある様々な「21日間」にまつわるトリビア(雑学)をフックにしたのだ。
この鉄道の広告だけじゃない。シリーズは他にもある。
• 「EXPERTS SAY, IT TAKES 21 DAYS TO FORM A HABIT.(専門家いわく、習慣が身につくには21日かかる)」
• ヨガのポーズをとる人物のイラスト。自己啓発的なメッセージと製品特徴の、見事なマリアージュだ。
• 「IN THE 18TH CENTURY, SHIPS TOOK 21 DAYS TO CROSS THE ATLANTIC.(18世紀、船が大西洋を横断するには21日かかった)」
• 歴史のロマンを感じさせる帆船のイラスト。時間の壮大さが、香りの持続期間の長さとシンクロする。
• 「MICROGREENS NEED 21 DAYS TO GO FROM SEED TO HARVEST.(マイクログリーンが種から収穫まで育つのに21日かかる)」
• 小さな鉢に育つマイクログリーンのイラスト。生命が育つ時間と、フレッシュさが続く時間が重ねられている。
どれもこれも、シンプルで洗練されたイラストと、たった一文の、人の好奇心を掻き立てるコピーで構成されている。そして最後に、まるで種明かしをするかのように「これ、うちの芳香剤が香る日数と同じなんだ」と、そっと教えてくれる。うまい。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/21-days-of-freshness
「数字」という名の、記憶のアンカー

では、なぜこのIkiのキャンペーンは、僕らの心をこれほどまでに強く掴むのだろうか? その秘密を、少し深掘りしてみたい。
まず第一に、「21」という具体的な数字が、強烈な「記憶のアンカー」として機能している点だ。アンカー、つまり船の錨(いかり)だ。マーケティングの世界では、顧客の頭の中に特定の情報(価格や数値など)を最初に打ち込むことで、その後の判断基準を無意識にコントロールする手法を「アンカリング効果」と呼ぶ。
「長持ちする香り」というのは、あまりに曖昧で、抽象的な概念だ。他社製品が「長持ち!」と謳ったところで、僕らの心には響かない。それは、比較対象もなければ、具体的なイメージも湧かないからだ。しかし、「21日間」と提示された瞬間、僕らの脳は具体的なスケール感を持つことができる。「3週間か…なるほど」と。
さらにIkiの広告が巧みなのは、この「21」という数字を、ただ提示するだけでなく、面白くて意外な事実(トリビア)とセットにしている点だ。人間の脳は、物語や関連性のない情報同士の意外なつながりを好むようにできている。世界最長の鉄道旅行が21日?へぇ!習慣化に21日?なるほど!
この「へぇ!」という小さな知的好奇心の満足が、製品情報と強固に結びつく。広告が、知的な興奮を与えてくれる「クイズ」や「豆知識」へと昇華するのだ。そして、このトリビアを誰かに話したくなったとき、嫌でも「Ikiの芳香剤」の話もセットでついてくることになる。これは、口コミを誘発する装置として、完璧すぎる設計と言えるだろう。
コンテクストの魔術師、あるいは風景への敬意

次に注目したいのは、このクリエイティブと「野立て看板(OOH – Out of Home)」というメディアの、完璧な相性だ。
考えてみてほしい。クルマで時速60kmで走っているとき、看板に目を奪われる時間は、ほんの数秒しかない。その一瞬で、伝えたいことのすべてを伝え、かつ記憶に残さなければならない。これは、至難の業だ。だからこそ、日本の多くの看板は、とにかく社名や商品名を大きく、分かりやすく表示することに終始してしまう。伝えたい情報を詰め込みすぎて、結局何も伝わらないという笑えない悲劇も後を絶たない。
しかし、Ikiの広告はどうだ? 大胆でシンプルなイラストと、巨大な文字で書かれた「21 DAYS」。それだけで、ドライバーの注意を引くには十分だ。視線を向けた先には、思わず読みたくなるような、好奇心を刺激する一文がある。
これは、メディアの特性、つまり「一瞬で通り過ぎる」というコンテクストを、完璧に理解し、計算し尽くした上で作られたクリエイティブなのだ。デジタル広告が、ユーザーの属性や行動履歴を元に、最適化された広告を「追いかけてくる」のとは対照的だ。野立て看板は、その場所にただ「存在」するだけ。誰の目にも公平に触れる。
広告を「発見」する体験に変える
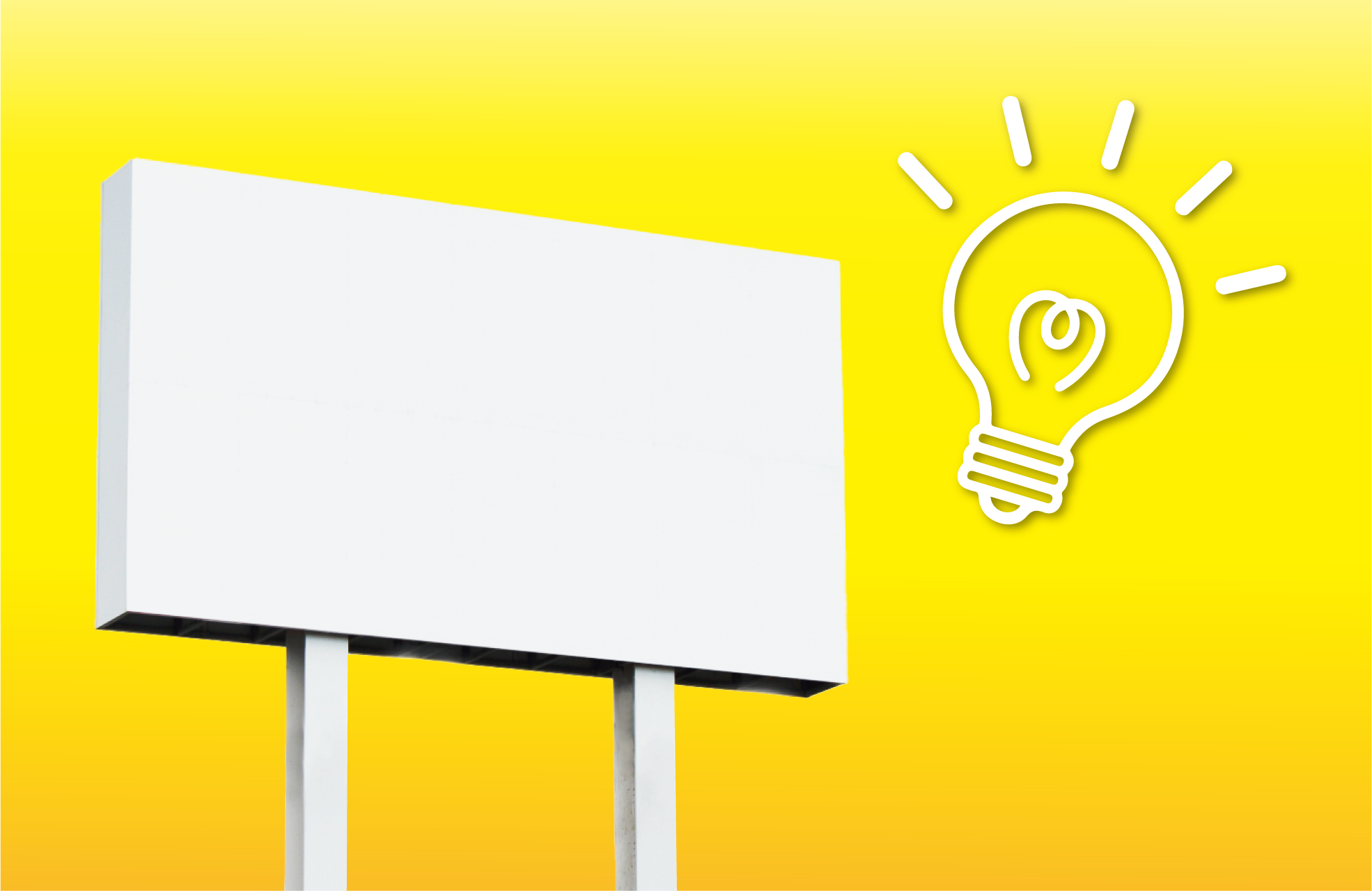
結局のところ、このキャンペーンの最も優れた点は、広告を「発見」という体験に変えてしまったことにある。
僕らは、この看板を見て、単に「Ikiの芳香剤は21日間香りが続く」という情報をインプットさせられたわけじゃない。「世界最長の鉄道旅行は21日かかる」という新しい知識を「発見」し、その喜びのおまけとして、製品情報を知ったのだ。このプロセスが決定的に重要だ。
人は、誰かに何かを「教え込まれる」のを嫌う。しかし、「自ら発見する」ことには快感を覚える。Ikiのキャンペーンは、この人間心理を見事に突いている。消費者が「へぇ!」と感じたポジティブな感情は、そのままブランドへの好意へと転化する。
僕らは今、情報の洪水の中にいる。スマートフォンを開けば、パーソナライズされた広告が次から次へと流れてくる。便利だし、効率的だ。でも、そこには「発見」の喜びは少ない。なぜなら、表示されるもののほとんどは、僕らの過去の興味の延長線上にあり、予測可能だからだ。
だからこそ、街角で偶然出会う、優れた野立て看板の価値は、むしろ高まっているのではないだろうか。アルゴリズムの支配から逃れた場所で、予期せぬクリエイティブに出会う。そのセレンディピティ(偶発的な発見の喜び)こそが、僕らの心を本当に動かすのだ。