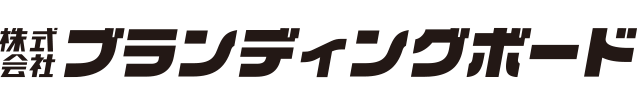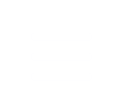コラム
Column

女王陛下、ごめんなさい。英国王室御用達シリアルが「新しい女王」にひざまずいた日
2025年6月18日

ロンドンの街を歩いていると、時折、思わぬ場所で“事件”に遭遇する。それは凶悪犯罪の話ではない。誰かの愉快で巧妙な企みが、野立て看板というかたちをとって、通行人にこっそり語りかけてくる瞬間のことだ。スマホの画面をいくらスワイプしても決して現れない、その場所にしかない物語。物理的な存在感を伴って、人々の記憶にじわりと染み込んでくる“置き手紙”。
さて、今回ロンドンで起きた事件は、これまで僕が見てきた中でも、とびきり痛快で、示唆に富んでいた。主役は、ひとりの若き歌姫と、ひとつの老舗シリアル。まるで出会うはずのなかった二つの世界線が、TikTokという現代の魔法によって交差し、やがて街の景色さえも変えてしまったのだから。
すべての始まりは、一枚のSNS投稿だった。いや、一枚というより、一本の短い動画だろうか。
現代の英国音楽シーンを語る上で絶対に欠かせないシンガーソングライター、Raye(レイ)。彼女の代表曲「Escapism.」がストリーミング再生10億回という金字塔を打ち立てた。スターが成功を祝う光景は珍しくない。シャンパンを開けるか、豪華なパーティを開くか。だが、彼女が選んだ祝福の方法は、僕たちの想像のはるか斜め上をいっていた。
なんと、その栄誉を讃えるSpotifyの「記念の盾」を、おもむろにシリアルの器にしてしまったのだ。銀色に輝くプレートの上に、ザクザクとシリアルをあけ、牛乳を注ぐ。そして、満足げにスプーンを口に運ぶ。その奇行ともいえる映像に添えられたキャプションは、こうだ。「God bless TikTok(TikTokに神のご加護を)」。
権威の盾を「器」に変える、反逆の作法

この一連のパフォーマンスは、あまりにも彼女らしかった。Rayeというアーティストは、ポップスターという枠には到底収まらない存在だ。大手レーベルとの契約をめぐる確執の末、そこから離脱し、インディペンデントとして自らの力で道を切り拓いた「反逆の女王」。彼女の成功の裏には、既存の音楽業界のシステムに対する抵抗と、TikTokという新しいプラットフォームを味方につけた戦略があった。だからこそ、権威の象徴である「盾」を、日常の象徴である「シリアルの器」として軽々と乗り越えてみせる行為は、彼女の生き様そのものを体現しているようだった。
そして、彼女がその“聖なる器”に盛り付けたシリアルこそが、この物語のもうひとりの主役、Weetabix(ウィータビックス)だったのである。
そもそもWeetabixってなんだ? と思った人のためにざっくり説明すると、これはただの朝食という言葉では片付けられない存在だ。1932年から英国の食卓に君臨しつづける、国民的シリアル。楕円形のビスケット状に固められたその姿は、英国人なら誰もが知る日常風景の一部。しかも、その品質の高さから英国王室御用達(ロイヤルワラント)の称号を得ている。つまり、本物の女王陛下も口にしたであろう、伝統と権威の塊。いわば、英国フード界の揺るがぬ“長老”だ。
片や、旧来の権威に中指を立て、自らのルールでゲームを制した新世代の女王、Raye。
片や、本物の女王陛下に愛され、90年以上も英国の伝統を守り続けてきた国民的長老、Weetabix。
この出会いは、事故だったのだろうか。それとも、必然だったのだろうか。
Rayeの投稿がSNSでバズを巻き起こしたとき、Weetabix社が取り得た選択肢はいくつかあったはずだ。見て見ぬふりをする。あるいは、公式アカウントで「おめでとう!」と当たり障りのないコメントを送る。だが、彼らはそのどちらも選ばなかった。この愉快な事件を、最高のビジネスチャンスと捉え、そして英国流のユーモアで満ちた、極上のアンサーを返したのだ。
老舗のウィット、故郷に咲く金色のレコード

数週間後、Rayeの故郷である南ロンドンの街角に、巨大な野立て看板が現れた。
描かれているのは、4枚のレコード。そのうち3枚は黒いアナログ盤だが、1枚だけが、まばゆいばかりの金色に輝いている。そのゴールドディスクのラベルには、こう刻まれていた。「Croydon’s Very Own(クロイドンが生んだ逸材)」。そして、ポスター全体を締めるコピーは、Weetabixの象徴的なキャッチフレーズ「Have you had yours?(あなたはもう食べましたか?)」をもじった、これ以上ないほど完璧な一言。
「She had Hers(彼女は食べたね)」
ここが、うまい。唸ってしまうほどに、うまい。
このキャンペーンの何がそんなに僕の心を鷲掴みにするのか。それは、看板に込められた多層的なメッセージと、その“企み”の巧妙さだ。
第一に、そのウィットに富んだ「返答」のセンス。Rayeの個人的な、そして少しクレイジーな行動に対し、同じレベルの遊び心で応酬する。これは、商品を一方的に宣伝するのではなく、カルチャーの“会話”に参加するという、現代のブランドが取るべき最もクレバーな姿勢だ。彼らはRayeの行動を「面白いじゃないか」と受け止め、その文脈に自ら乗っかった。
第二に、その「場所」の選び方。この看板は、ロンドンの中心地、オックスフォード・ストリートには立っていない。Rayeが育った故郷、クロイドンにだけ掲げられた。これは、広告を認知拡大という一面的な役割に留めず、「物語」を紡ぐための舞台装置として使っている証拠だ。Weetabixは、Rayeに対して「君の成功を、君の地元は誇りに思っている」という、極めてパーソナルで、心温まるメッセージを送った。それは、故郷に錦を飾るという、万人の心を打つストーリーの演出にほかならない。
そして第三に、その「敬意」の示し方。金色のレコードは、Rayeの功績に対する最大限の賛辞だ。Weetabixは、彼女を話題のインフルエンサーとして消費したのではなく、ひとりの偉大なアーティストとしてリスペクトし、その成功を“公式に”祝福した。これは、伝統あるブランドが、新しい世代の才能に「君こそが本物だ」と勲章を授与する儀式のようにも見えた。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/she-had-hers
デジタルとリアルを往復する、現代の“置き手紙”

思えば、この一連の流れは、デジタルとリアルの美しい往復運動だ。
始まりはTikTokというデジタルの世界。それがWeetabixというリアルな商品につながり、企業のマーケティングチームを動かし、最終的にクロイドンの街角という物理的な空間に「金色のレコード」というリアルな景色を生み出した。ネット広告が一瞬で流れ去っていくこの時代に、街角の看板はじわじわと、そして確実に人々の記憶に根を張る。
この出来事は、僕たちに何を教えてくれるのだろう。
それは、デジタル一色の世界だからこそ、人は「本物の現場」や「物理的な存在感」に飢えているということかもしれない。そして、最高の広告とは、商品を売ることではなく、“共犯者”を作ることなのだ、と。Weetabixの看板を見たクロイドンの人々は、きっとこう思っただろう。「私たちの街のRayeは、すごいだろう」と。彼らはもはや消費者という立場を超え、RayeとWeetabixが紡ぐ物語の、誇り高き目撃者であり、共犯者なのだ。