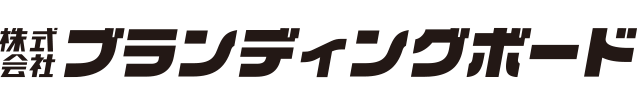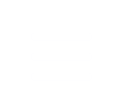コラム
Column

ロンドンの路地裏で出会う、野立て看板の愉快で巧妙な企み
2025年6月16日

道に迷ったとき、人はしばしば看板を探す。いや、たとえ道に迷っていなくても、僕はしょっちゅう「何か面白い看板はないか」とキョロキョロしてしまう。野立て看板――それは、どこかの誰かが僕にこっそり語りかけてくる“置き手紙”のようだ。スマホに映らない情報。グーグルマップが絶対に表示してくれない現場感。やっぱり、実物の広告、アナログの看板ってのは、なかなか侮れない。
さて、今回はちょっと、食いしん坊たちが鼻をひくつかせているという噂の「Belazu(ベラズ)」のOOHキャンペーンを覗き見してみようと思う。ほら、そこの角を曲がると、きっと君も出会うはずだ。小さな“異世界の入口”に。
シェフの街に、Belazuの旗が立つ夜

そもそもBelazuってなんだ? と思った人のためにざっくり説明すると、地中海とか中東あたりの食材を専門に扱っている、イギリス発のブランドだ。ロンドンのレストランではプロのシェフたちが「俺の料理はこのオリーブオイルなしでは語れない」と豪語している(多分)。そんなBelazuが、2025年の夏、ついに「野立て看板」で勝負をかけてきた。
その狙いはずばり、“実験好きなシェフ”や“食にうるさい通行人”の心をズバッと射抜くこと。やるじゃんBelazu、ターゲットがしっかりしてる。設置場所も渋い。バラ・マーケットやショーディッチ、アッパー・ストリート……食のホットスポットのど真ん中だ。さらには有名レストラン「Trinity」とか「Carmel」「Berber & Q」の近くにも。さすがロンドン、クールな食の街。しかも、小売店(ウェイトローズやテスコ)のそばにも置いてくるあたり、「お前、さっきこのレストランで食べたやつ、今からスーパーで買えるぞ?」と耳打ちしてくる感じがしてニクイ。
“プロの現場と君の台所が地続きになる瞬間

看板をみる。大きな黒い文字。「In the most SOUGHT-AFTER RESTAURANTS and TASTE OF LONDON」だって? 誇張じゃなく、本当に“レストランと同じ食材が君の家に届く”というメッセージをドーンと投げかけてくる。そこに、シェフの手元や、グリルで焼かれる大きなエビ、瓶詰めのオリーブやハリッサの写真が彩りを添える。
そして……おやおや、この手書き風のメモは何だろう?「In season: seabass, bream, prawn」みたいなちょっとした季節の食材メモや、「Large tiger prawn, cook for 5–8」なんて調理のヒントまで。思わず、「あれ、この看板、厨房の中の秘密を暴露している」と唸ってしまう。つまり、現場の“温度”を感じるのだ。広告は普通“現実感”を隠そうとするものだけど、このBelazuの看板は逆。プロの現場と、買い物客の日常を、まるで地続きにしてしまう。
ここがうまい。看板というのはただ目立てばいいわけじゃない。広告の“嘘くささ”がすぐにバレる時代だからこそ、「おい、これリアルだぞ」と感じさせる演出が求められる。Belazuの野立て看板には、そんな“生活者の納得感”がちゃんと仕組まれている。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/belazu-targets-experimental-chefs-with-summer-ooh-push
場所とメッセージの“化学反応”――野立て看板の本領

もう少し考えてみよう。なぜBelazuは、ロンドンのど真ん中、しかも有名レストランやスーパーの近くにわざわざ看板を出すのか?
これ、実は極めて戦略的だ。要するに「ここを通るやつは全員ターゲット」と開き直ってるわけじゃない。本気で“料理好き”に出会いにいってる。大手の野立て看板がしばしばやりがちな「とにかく人通りの多い場所でドーン!」ではなく、「その分野に特化した“現場”に突っ込む」やり方。
これが実際どんな効果を生むのか?
たとえば、料理人が店に入る前、あるいは帰り道に「お、Belazu使ってるレストランだ」と気付く。一般の食通たちは「この食材、プロ御用達らしいけど、家でも使える?」と興味を持つ。その場で近くのスーパーに立ち寄り、ハリッサやオリーブオイルを手に取る。「さっき見たばっかりのやつだ!」と。
広告って、こういう“気付き”を起こした瞬間が一番強い。Belazuはまさに、「今すぐ買える」動線を、街のリアルな空間でつくっている。デジタル広告じゃ絶対真似できない「地の利」。しかも、「Trinityのシェフと君のキッチンが同じ世界線にいる」という体験。看板1枚で、ブランドストーリーと現場体験をミックスさせてしまう。
“商品”ではなく、“共犯者”を作る

さらについ唸ってしまうのは、「商品を売る」のではなく、「君も仲間に加われ」という目線が徹底していることだ。看板のあちこちに、シェフのリアルな仕草や厨房の雰囲気が散りばめられている。普通は「プロ仕様!」とだけ強調してしまいがちだけど、Belazuは「プロと同じもの、君もどうぞ」と手を差し伸べてくる。
この心理的距離の近さが、このOOHデザインの肝だと思う。広告を“壁”ではなく“扉”に変える。料理の世界に飛び込む“共犯者”を増やす。見る者に「俺もやってみようかな」と思わせる妙技こそが、野立て看板の真骨頂なのだ。
デジタル時代に「リアルな広告」が求められる理由

世の中がデジタル一色になり、AIが生成した広告がSNSを埋め尽くす。そんな時代だからこそ、人は「本物の現場」「物理的な存在感」を無意識に求めてしまう。Belazuの看板は、その渇望をピタリと突いている。
ネット広告なら一瞬で流れて消えるが、街角の看板はじわじわと記憶に残る。しかも、食の“聖地”ロンドンで、しかも“現場”の空気ごとパッケージングしてくるBelazuのやり方は、「広告の未来はやっぱりリアルだ!」と背中を押してくれる。
最後にもう一度。野立て看板は、ただの広告じゃない。君の通り道に現れる“選ばれし情報”だ。それは、誰かの好奇心をそっと焚きつける“舞台装置”でもあるのだ。