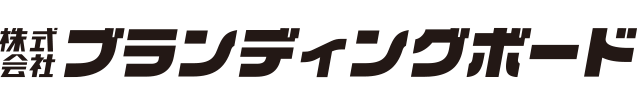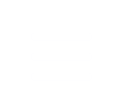コラム
Column

マクドナルドの“超ドアップ看板”が語る、OOH×ブランディング
2025年4月3日
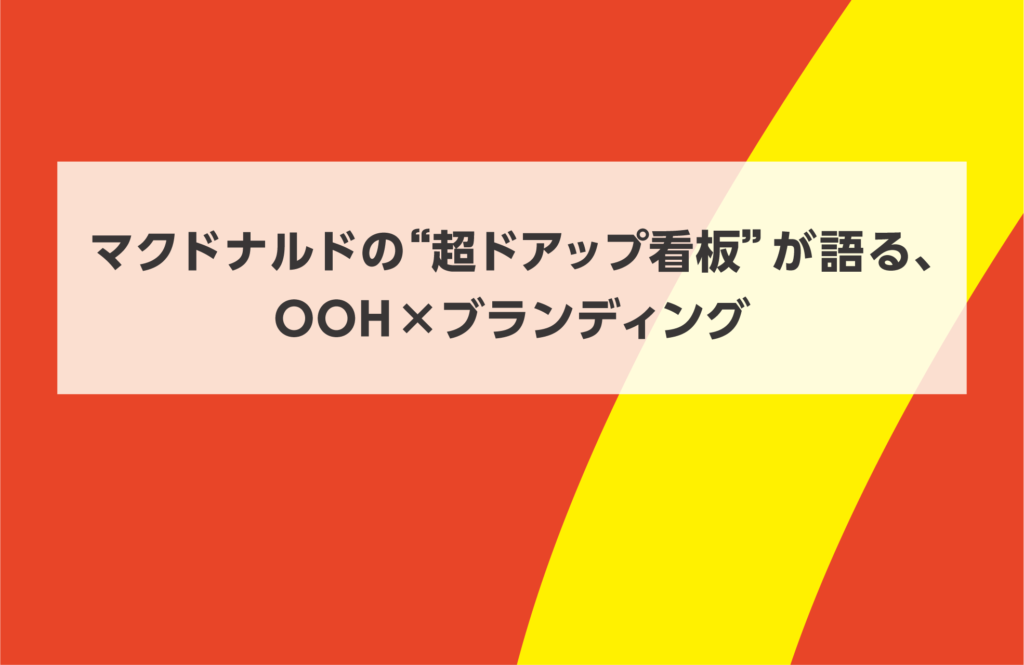
街角や地下鉄の通路、ビルの壁面など、世界のいたるところで見かけるOOH(アウト・オブ・ホーム)広告。実はSNS広告全盛の時代にあっても、人々の目を奪う強力なメディアとして見直されている。なぜなら、街を行き交う瞬間に“強制的に視界に入る”という物理的特性があり、しかも、デザイン次第では記憶に深く刻まれる余地も大きい。
そんなOOHの特徴を最大限に活かしたのが、マクドナルドUKの“朝マック”広告キャンペーンだ。マクドナルドの朝食メニュー、エッグマフィンやハッシュポテトをありえないほど“ドアップ”に撮影したビジュアルが、巨大なパネルとして街中にドドーンと登場。見る人は最初、「これ、何?」と思わず足を止める。その後、「あの金色のチーズはもしや……」「この半熟の卵は……」と想像力を膨らませ、「朝マックか!」と気づく。その瞬間誰もが、思わず朝マックを食べたくなってしまう。たった一枚のビジュアル看板で、通行人は強烈に“おいしそう”な感情を刺激されるわけだ。
本コラムでは、なぜこの超アップ広告がここまで目を引き、しかもブランディングや広告効果の観点で優れているのかを掘り下げてみたい。そこには、マクドナルドがこれまで培ってきたブランド力への自信と、“飾らない素材感”そのものに訴える巧みな戦略が隠れている。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/you-ll-know-them-when-you-see-them
これぞOOHの醍醐味――視覚を根こそぎ奪う“超アップ”手法

通常、ハンバーガー広告といえば、商品全体を見せて「どんな具材が入っているか」を分かりやすくするのがセオリーだ。だが、今回のマクドナルドの看板は、その常識をあえて捨て去った。パンや卵、チーズ、ハッシュポテトといった“パーツ”をありえないほど拡大し、看板の全面に貼り付ける。ぱっと見、「これ何の写真?」と戸惑うほどの超クローズアップ写真だ。
しかし、その戸惑いこそがこの広告の狙い。多くの看板が商品写真と価格やコピーを詰め込んでいる中、このキャンペーンは“余計な情報”をあえて削っている。見えるのはテカテカに光るチーズの断面や、サクサク感が伝わるハッシュポテトの表面――いわば“味覚をそそる質感”だけだ。それゆえ、遠目からでも「何か巨大な食べ物?」と疑問を抱かせ、近づくにつれ「ああ、マクドナルドの朝食メニューか!」と理解させる二段階の仕掛けが機能する。
OOHでは、文字数や派手なコピーよりも、“一目見た瞬間のインパクト”が重視される。人は通勤や買い物の途中で看板を見るため、じっくり読む時間が少ない。だからこそ、この広告は“素材の迫力”に一本化している。エッグマフィンの焼き色やチーズの溶け具合、ハッシュポテトのカリッとした粒子感といった、通常なら意識しないようなディテールを強調することで食欲をダイレクトに刺激するのだ。
ロゴやコピーを排除――それでも“マクドナルド”とわかる自信

興味深いのは、この超アップ看板には、ロゴやキャッチコピーが入っていない点だ。多くの広告では「マクドナルド」「朝マック」「新発売」などのテキストがドーンと大きく表示されるはずだが、ここでは商品名すらはっきり書かれていない。それでも、「マクドナルドの朝食メニューだ」と分かる人が多いのではないだろうか。
これはすなわち、ブランド自体が確立されているがゆえの大胆さともいえる。世界中の人にとって、エッグマフィンやハッシュポテトといった“マクドナルドらしい”ビジュアルは、ブランドを連想させるアイコンのようなものだ。ロゴなしでも「朝マックだ!」と直感的に気づく認知度があるからこそ、こんなに割り切ったシンプルデザインが可能になるわけだ。
逆に言えば、このアプローチはブランド力を誇示する効果もある。消費者は、「ロゴもないのにマックと分かるなんて、すごい存在感だ」と再認識する。普通の企業が同じ方法をとっても、「何の広告か分からない」で終わるリスクが高いが、マクドナルドほどのグローバルブランドならではの戦略だ。
食欲をそそる“素材感”重視のデザインが作るブランディング効果

マクドナルドの朝メニューは、ヘルシーな食事というより“手軽でおいしい”イメージが強い。朝の短い時間にパッと食べられる“元気の源”として親しまれている。その世界観を野立て看板で出すには、商品の味や香り、温かさをいかに伝えるかが鍵になる。実際に、この巨大アップ画像を見れば、黄身の鮮やかな色味やマフィンの焼き目、チーズのとろけ具合などがリアルに感じられ、通りがかる人の「朝ごはん、まだだったな」という食欲を呼び起こす。
この広告の面白いところは、見れば見るほど「食べたい」気分になる点だ。多くの広告は、テキストで「おいしい」「お得」と書くが、このキャンペーンではビジュアルの迫力だけでそれを伝える。コンセプトとしては“素材のテクスチャ”を全面に押し出し、「朝マック」の“焼きたて感”や“ふっくら感”を感じさせることで、最終的にはブランド全体の“おいしさ”イメージを強固にする。つまり、単なる一時的な販促に終わらず、“朝食=マクドナルド”という刷り込みを狙うブランディング効果があるのだ。
OOH×ブランディングの革新性――情報過多の時代にこそ一枚で勝負

現代はSNSやWEB広告の乱立により、消費者の注意力が短くなり、広告疲れが進んでいるともいわれる。そんな中、この“超ドアップ”という手法は、逆に新鮮で、オンライン広告とは違うアプローチで目を奪うのに成功している。しかも、マクドナルドがあえて文字情報を削り、ビジュアルだけでコミュニケーションを完結させている点が、これまでの広告常識を覆す革新性といえる。
1. “余白”ではなく“極端な拡大”を余白的に使う
一般的なミニマルデザインでは“余白”の活用が重視されるが、この看板は逆に“素材の極大化”によって結果的に他要素の入り込む余地が無いという状態を作っている。背景も説明もいらない、ただ「このおいしそうな断面を見ろ」という潔さが、情報が飽和した時代において一種の清涼感を与えているわけだ。
2. デジタル連携を想定した二次拡散
実際に、この巨大サンドイッチ看板がSNS上で拡散され、人々が「こんな広告あるんだけど……」「ハンバーガーが壁一面に!」と写真を投稿し合う姿が見られたという。OOHがソーシャルメディアで話題化し、さらにバイラル効果が働くという構図だ。デジタル広告をあえて使わずとも、面白ければ自然とオンラインに波及する時代を象徴しているとも言える。
3. 小規模ブランドにも応用可能なヒント
もちろん、マクドナルドほどのブランドパワーがない企業が同じ手法を取った場合、「何の広告か分からない」とスルーされるリスクがある。とはいえ、「余計な情報を詰め込まず、ビジュアルで感情を揺さぶる」という考え方は、小規模ブランドの野立て看板でも応用しやすい。たとえば、パン屋なら焼きたてパンのクローズアップ、医院なら医療技術や安心感を象徴する診療中の手のクローズアップ、といった具合に、“素材”や“特徴”そのものをフォーカスしてインパクトを作るやり方が考えられる。そこに少しの文字を添えるだけで十分印象付けられる。
ビジュアル一発で“朝のワクワク”を呼び起こす力

朝の通勤路で、大きく拡大された卵やチーズの写真が目に飛び込んでくると、自然と「おなかすいた…」「朝マック、アリかも」と思ってしまう人は少なくないだろう。わずか数秒の接触でも、人の感情をここまで動かせるのが、OOH広告の強みだ。しかもこのマクドナルドの例は、ブランディングという点でも秀逸で、ロゴを見せなくても「マックの朝食だ!」と一瞬で認識させる企業力を活かし、“余白なき超拡大”のビジュアルで勝負に出ている。
これは、いわゆる“デジタル広告の飽和”に対する一つの解答とも言えるかもしれない。スマホで流し見される広告よりも、街角の壁を圧倒する巨大な“サンドイッチの断面”は、人々の注意を一気にさらい、SNSで二次拡散され、ブランドのイメージをさらに強固にするという連鎖を生むのだ。