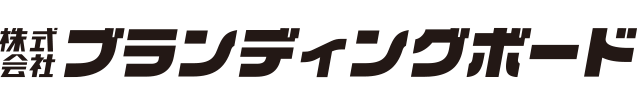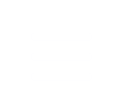コラム
Column

「苦い真実が、子どもを守る?」――デュラセルの電池看板がもたらす意外なメッセージ
2025年4月1日
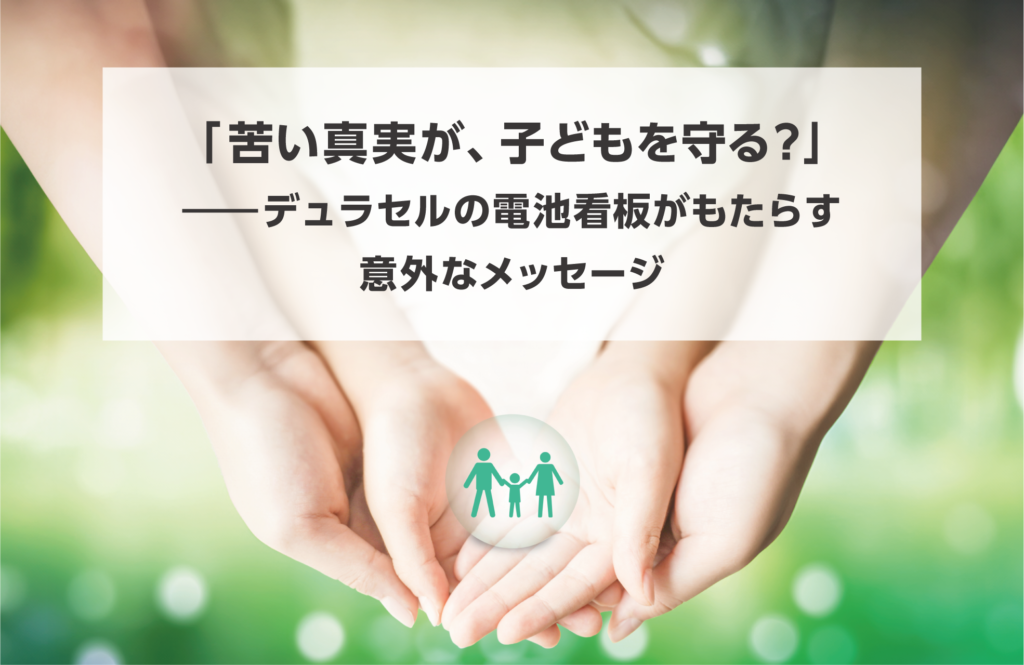
わたしたちの暮らしは、便利さを求め続けるあまり、ときに思いもよらぬ落とし穴をはらんでいる。とりわけバッテリーや電池の存在は、現代の家電ライフを支える要のようなものだ。体重計、リモコン、車のキーフォブ、さらには炎の出ないキャンドル――いまやリチウムコイン電池はあらゆる家庭に潜り込み、わたしたちの身近に溶け込んでいる。その一方で、「子どもが誤って飲み込む」というシンプルだが恐ろしい事故が急増していることは、意外と知られていない事実だ。
電池を飲み込む――そんな危険が、本当にあるのか?と思う人もいるかもしれない。けれど、実際に数字は如実に示している。2002年以降、こうした事例は世界的に4倍以上にも増加しているのだ。小さな子どもの好奇心は旺盛で、目新しいものを何でも口に入れてしまう。あるいは、ほんの一瞬の隙に、つるりと滑り込ませてしまう――想像すると背筋が寒くなるが、これが「現代の豊かな暮らし」の裏側に潜む、深刻なリスクである。
そんな暗い問題に対し、世界的な電池ブランドであるデュラセルは、とびきりポップで遊び心あふれる“屋外広告キャンペーン”を世に送り出すことを決めた。その名も「Bitter Truths(苦い真実)」。子どもを危険から守る“苦味コーティング技術”をアピールしながら、家庭の安全という重要テーマを、まるで絵本のようなデザインとショッキングなコピーのギャップで強烈に訴えるというアプローチだ。
■参考サイト:https://www.adsoftheworld.com/campaigns/bitter-truths
“苦い真実”が生む安全技術

デュラセルが開発したリチウムコイン電池の苦味コーティング技術は、世界で最も苦い物質として知られる「ビトレックス(BITREX)」を活用している。もし乳幼児が誤って口に入れてしまった場合、激しい苦味によってすぐに吐き出すよう促すのだ。幸いこの成分は無毒でありながら、子どもの舌にはたまらないほどに「まずい」らしい。子どもというのは、どれだけ「ダメだよ」と言われても、興味がわくと本能的に行動してしまう生き物。だからこそ、こうした物理的かつ直接的な“苦味”でガードするという発想は理にかなっている。
さらに、この技術を実用化しただけでなく、当のデュラセル自身が「業界唯一の苦味コーティング技術を持った電池メーカー」としてその存在を明確に訴えている点も見逃せない。安全機能をここまで前面に打ち出し、さらにはビジュアルやコピーで遊び心まで添えて発信するのは、“子どもの誤飲事故”を社会問題として真正面から扱おうという強い意志の現れでもある。
メルヘン×辛辣コピーが光る看板デザイン

さて、このキャンペーン「Bitter Truths」では、複数の著名イラストレーターやデザイナーが参加している。ディズニー作品にもかかわったカナダ人アーティストのマキシン・ヴィー氏や、ベストセラー絵本『クマとピアノ』を手がけたデヴィッド・リッチフィールド氏。さらに3Dアニメーションを制作するアーケード・スタジオが連携しているというから、そのビジュアルの完成度の高さはお墨付きだろう。実際、街に設置された屋外広告は、ピンクやパステル調を中心としたファンタジー感あふれる彩りで、人目を引きつける。“子ども向けの絵本”を連想させる柔らかくてかわいらしい世界観。それだけ見れば、まるでおとぎ話の扉が開くかのようなワクワク感が漂っている。
しかし、そこに添えられたコピーはこうだ。「Mummy loves your brother’s birthday more than you(ママはあなたよりも、あなたの兄弟の誕生日のほうが好き)」――もう、なかなかに辛辣だ。「なんて残酷な言葉!」と大人でもぎょっとする。思わず「この可愛い雰囲気と真逆のメッセージは、一体どういうことだ?」と足を止めてしまう人も多いだろう。まさに、この落差こそがキャンペーンの真骨頂。子どもの無邪気な世界に見える一枚のイラストに、実は大人でも受け止めにくい“苦い真実”が隠されている。こうしたギャップを狙うことで、デュラセルの「飲み込んだらもっと苦いよ」という安全機能をユーモラスかつショッキングに伝えているわけだ。
“苦味コーティング”を伝えるための感情アプローチ

子ども向けの絵本風ビジュアルに、残酷なコピー。この二つが同居するからこそ、「なぜこんな可愛いイラストでこんな冷酷なことを言うのか?」という疑問を投げかけ、結果的に人々を惹きつける仕組みになっている。広告は、一瞬の目撃で勝負が決まることも多い。とくに屋外広告では、通りすがりの人がじっくり読むのは難しい。だからこそ、ひと目で「えっ?」と驚かせる仕掛けが重要なのだ。
今回のコピーが大人をショックに導き、そしてターゲットである親たちは「自分の子どもが誤って電池を飲むかもしれない」という、より深い不安に想像を巡らせるだろう。すると、「そうか、デュラセルの電池には苦味がついているのか。だから安心なのか」と納得につながる。子どもが誤飲する事態の恐ろしさを改めて考えさせられたうえで、「しかし解決策がちゃんとあるんだ」と感じられるなら、ブランドへの好感度や信頼感は高まる。これこそ、感情へのアプローチが効果を発揮する典型例だ。
安全性のメッセージを「シリーズ化」して広げる戦略

この看板だけで終わらないのが、デュラセルの狙いでもある。「Bitter Truths(苦い真実)」というタイトルから連想される通り、同じ世界観で“別の苦い言葉”を載せた広告が今後も続々と登場する。いくつものパターンを街のさまざまな場所に散りばめたり、SNSで拡散したりすることで、人々は「今度はどんな“苦い現実”が描かれているんだろう?」と興味を持つ。結果的に、少しずつデュラセルの取り組みを知り、「苦味コーティング技術=子どもを守るための救世主」という図式が、じわじわと浸透していくわけだ。
そしてこの「シリーズ広告化」は、“記憶の定着”において非常に効果的だとされる。人の脳は「繰り返し見聞きするもの」を重要情報とみなし、自然と覚え込んでいく。異なるビジュアル・異なるコピーが似たテイストで展開されることで、「子どもの誤飲防止はデュラセルがリードしている」という認識が、時間をかけて定着していくのである。
“苦い”からこそ、守れる未来がある

誤飲事故は、当事者になって初めて、その怖さを身に染みて実感するものかもしれない。しかし、そこに至る前に防げるのであれば、それがいちばん良いのは言うまでもない。デュラセルの「苦味コーティング電池」は、子どもが嫌がる不快感を利用して、彼らの未熟な行動をフォローする仕組みだ。小さな疑問や不満(「ママはあっちの誕生日のほうが好き」など)を、子どもがまだ理解しにくい苦い現実のように、誤飲事故も“小さな子どもには理解しづらいリスク”である――だからこそ、物理的に排除しよう、というメッセージが込められている。
奇をてらったように見えるデザインとコピーの裏には、巧妙に計算されたクリエイティブの意図がある。デュラセルがその電池を通して見せるのは、テクノロジーだけに頼るのではなく、親や社会全体で「子どもを守ろう」というメッセージだ。ビジュアルの可愛さに隠れているのは、実はものすごく真面目で本質的な課題。そこに気づいてほしいがための「Bitter Truths」なのである。